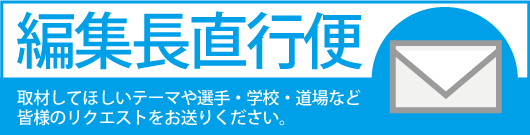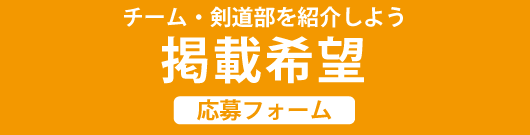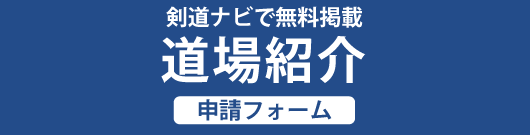個人戦3位2名、地力のあるチームが予選リーグからの激闘を制する
茨城県・水戸葵陵高校が剣道界で知られるようになったのは平成7年、平岡右照がインターハイ個人戦優勝を果たしてからのこと(当時は水戸短大附属水戸高校)である。
この頃から団体戦でもインターハイの常連となった。初の3位入賞を果たすのは平成14年、地元茨城で行なわれたインターハイだった。
その4年後、水戸葵陵はついに全国の頂点に立つ。春の全国選抜、夏の玉竜旗を制し三冠を狙う九州学院をどこが止めるかがこの年の焦点だったが、予選リーグに大きな注目カードがあった。
のちに全日本選手権を制する西村英久が大将をつとめる九州学院は、強豪桐蔭学園(神奈川)と同じ予選リーグを戦い、直接対決は引き分けだったがもう1試合の結果で及ばず敗退する。
一方水戸葵陵も福大大濠(福岡)、東海大第四(北海道)との死のリーグとなり福大大濠と引き分けながら何とか勝ち進んだ。
決勝は水戸葵陵と桐蔭学園の関東対決となる。すでに桐蔭学園は平成14年にインターハイを制覇、翌年連覇を達成していた。
水戸葵陵は大将遅野井直樹と副将金井佑太が二枚看板。2名ともが個人戦の準決勝に進出し、ともに3位に留まったが、あわや同校決勝かとも思われるほどの力を持っていた。それだけに前の3人がどう戦うかが課題だった。
小曽納匠の二本勝ちで好スタートを切った水戸葵陵は、次鋒戸崎聖が会心のメンで王手をかける。
2年生同士の中堅戦は桐蔭学園の村上雷多に中山直樹が二本負けを喫するも、金井が引き分けでつなぐ。
大将戦、遅野井に対するのはこの大会で個人2位に入賞した成田辰訓。遅野井はその成田にメンを浴びせるや、さらに二本目のひきメンを奪い、ついに念願の優勝旗にたどり着いた。
この時期は関東優位が続き、平成14年の桐蔭学園から5年連続で関東のチームが王座に着いている。
剣道界の勢力地図が書き換えられたように感じられた時期だが、やがて九州学院を中心に剣道王国九州が復活してくる。
水戸葵陵は国士舘大学を卒業した君島範親監督がゼロからチームをつくり、就任からちょうど20年目、九州勢を中心とする強豪への挑戦を続けた末に栄冠を手にした。
平成21年には2回目の優勝を果たし、その後も全国上位の力を保っている。