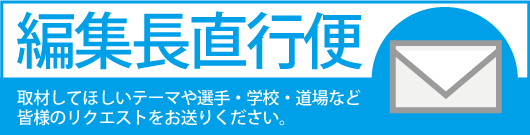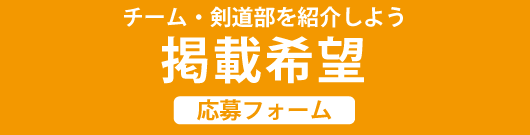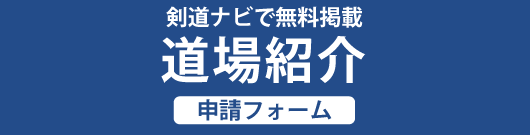剣を用いる二つの武術

江戸時代中期に誕生し、竹刀と防具を用いた武道である剣道は今日まで続いており、国際的な大会が開かれるまでの知名度を得ています。
ですが、それとは別に今日まで続いている居合道について知っている方は少ないかと思われます。
今回はあまり一般には知られていない居合道の歴史や現在の状況、意外な共通点などを紹介していきます。
■居合道とは
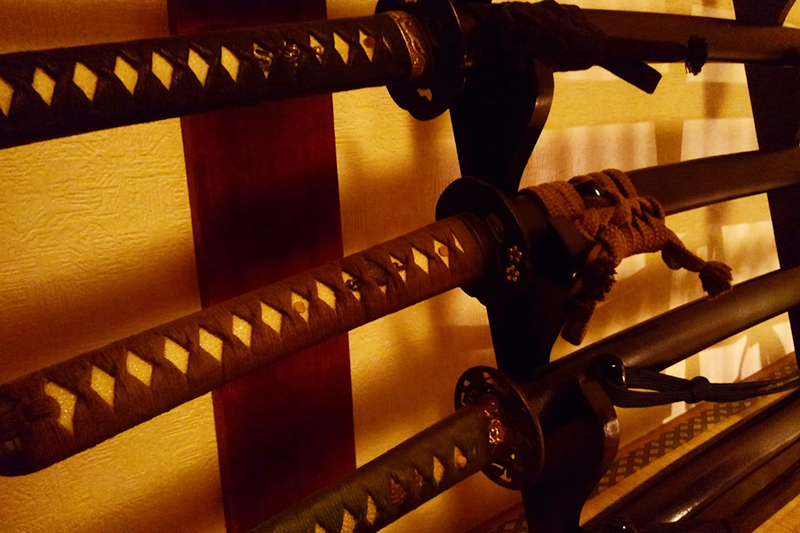
居合とは刀を鞘に納めて座っている状態から日本刀を素早く抜刀し、相手に一撃を加えるか、あるいは相手の攻撃を受け流して反撃に繋げるかという武道の事を指します。
そのため、流派によっては現在でも座っている状態を基本とし、立って抜刀する事を立合としている所もあります。
居合道とは、この武術を習得する過程において、人間の人格形成を目的としています。
■居合道の歴史

居合道の歴史は江戸中期に誕生した剣道をさらに遡り、戦国時代~江戸初期の頃から始まります。
この頃になると、武士の活躍の場は戦場から城や街の中といった、普通の人が生活する場所に変わりました。
つまり、刀を鞘に納めている状態が普通になったことで、鞘から刀を抜く段階からの技を追求する居合・抜刀術の重要度が増してきたのです。
居合術は剣客林崎甚助がもっとも古い流派を作ったとされ、居合を専門とした流派が各地に誕生します。
しかし、明治維新後の新政府によって日本刀は取り上げられ、居合術は存亡の危機に立たされます。
剣道は西南戦争における抜刀隊の活躍もあり、政府の中で積極的に取り組んでいくという流れが出来ました。
しかし日本刀を使う居合道は剣道の中に組み込まれる事は無く、各地の流派が継承していきます。
そんな状況下で明治28年に結成された大日本武徳会によって居合術は他の武術と共に振興されるようになります。
優れた使い手には称号を与える制度を作り、居合術は存続していきます。
太平洋戦争の敗戦によって大日本武徳会が解散されると、日本刀も多くが没収され廃棄されることになります。
このため、占領が解除されて全日本剣道連盟が発足されても居合術は連盟の中に含まれていません。
そこで、1954年に無双直伝英信流第20代宗家河野百錬が中心となった全日本居合道連盟が発足されることになります。
この頃から、居合術は居合道と呼ばれるようになります。
現在国内では、全日本居合同連盟の他に、大日本居合道連盟、日本居合道連盟、全国居合同連盟といった複数の団体が存在し、その連盟独自の演武大会や段級位審査を行っています。
■居合道の試合形式

居合道にも試合はありますが、剣道と違い、斬り合う形式の試合は執り行いません。
段位ごとに各連盟の規定技や所属している流派の形を演武し、審判員の上げた旗で評価して勝敗を判定します。
団体によっては高段位だと人数が少なく試合が成立しにくいため、演武だけで終了する所もあります。
試合において着用するのは主に道着と袴です。高段位になると正装として紋付や仙台平の袴を着用することもあります。
居合道の特徴として、高段位は真剣を用いた演武を行う事もあります。
一方で初心者や段位が低い者、一般的な練習の時は居合刀と呼ばれる専用の刀で練習をします。
居合刀とは真剣ではない日本刀の事を指します。
模造刀との違いは、観賞用では無く居合道に用いても壊れない強度を持ち、あまり派手な装飾を施されておりません。
実は真剣との違いはほとんど無く、形やパーツの種類からどちらも日本刀と呼ぶ基準を満たしております。
真剣との違いは、切れないように刃が付いているかどうかだけであるため、取り扱いには大変注意が必要になります。
居合刀の特徴して樋(ひ)が上げられます。
樋とは刀身に掘られた溝の事ですが、模擬刀や居合練習刀にはありません。
この樋があると、刀身の強度を落とさずに軽量化が出来る上に、刀を振った時の風きり音が大きくなるというメリットがあります。
そのため、居合道の試合では多くの選手が樋がある物を使用しています。
また、剣道の竹刀と違い、居合刀には基準となる大きさや決まりはありません。
所属している流派や団体、性別、年齢、体の大きさによって適切な長さや重さが変わってくるため、多くの方がオーダーメイド品を注文します。
■居合道と剣道の意外な共通点

歴史的に見ても、日々の取り組みや試合の形式も剣道と居合道は同じ剣を扱う競技でありながら違う点が幾つもあります。
対人形式の打ち合いを主体としている剣道に対して、居合道はあくまでも型の完成度や美しさを競うものであるという点が最大の違いであると言えます。
しかし、剣道と居合道にはある共通点があります。それはどちらも「道」である事です。
昔、剣道は剣術と呼ばれ、居合道は居合術と呼ばれていました。
他にも柔道は柔術、抜刀道や弓道も抜刀術や弓術と呼ばれていました。単に言葉が「術」から「道」に変わっただけと思われますが、実は違います。
元々、剣術や居合術は相手を殺すための技術として発達していました。それらを一纏めに言えば「武術」とは相手を倒す事を目的としていたのです。
しかし、江戸時代が終わり古い価値観から新しい価値観へと変化していきます。
相手を倒す事が目的とした「術」から、技術の習得や勝ち負けでは無く、それを通じた人格形成を目的とした「道」へと変化したのです。
「道」という漢字は首としんにゅうから成っています。この首とは人を表し、しんにゅうは往来を表しています。
この事から「道」という字には何度も繰り返す事で1つの境地へと達するという意味が込められています。
一見、違うことだらけのような居合道と剣道ですが、どちらも武道を習う事で自分を高めるという点では同じなのです。
■まとめ

・居合道とは「刀を納めた状態から素早く抜刀し、一撃を加えるか相手の攻撃を受け流す」ことを目的とした武道
・居合道の試合は対戦形式ではなく演武を行い、その”形”に対する評価で勝敗を判定する
・鍛錬を通じて自身を成長させるという意味で剣道と居合道には通じるものもある
居合道は剣道ほど盛んに行われているとは言い難いですが、今でもきちんとした団体が存在している武道です。
他のスポーツ・競技ほど激しく体を動かすことがないため女性や年配の方にも親しまれやすく、