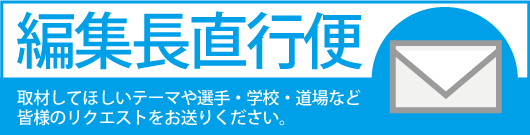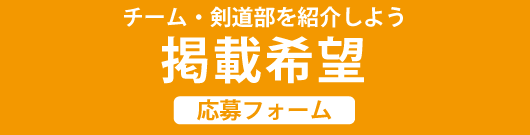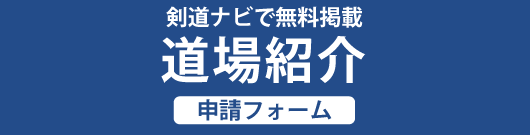剣術の”技”
アニメやマンガでは、登場するキャラクターが剣を使って放つ、いわゆる”必殺技”が存在します。
るろうに剣心の「九頭竜閃」や「牙突」、ダイの大冒険の「アバンストラッシュ」などなど…これらの必殺技に憧れて子どもの頃に真似してみたという方も多いと思います。
それらのほとんどはあくまでフィクションですが、剣道の元となった剣術には実際のところ様々な”技”が存在します。
■佐々木小次郎の得意技・燕返し
フィクションの世界だけでなく実際の剣術にも様々な技がありますが、その中でも特に有名なものとしては「燕返し」があります。
あまり詳しくない人でも名前は聞いたことがあると思いますが、巌流島で宮本武蔵と決闘したことで有名な「佐々木小次郎」の技として知られています。
実はこの燕返しというのは後から作られた刀法の名称で、実際は中条流という古流に伝わる秘剣「虎切刀」とされています。
燕返しという技は、刀を相手の真っ向から垂直に地面スレスレまで斬り降ろします。地面まで斬り降ろすのは、要するにフェイントの意味を持ちます。
目の前にいる相手がカラ振りしたと思わせた後、その瞬間に地面スレスレにある刀の刃を上部に返して、相手の股から顎まで斬り上げるのです。
下からの攻撃は、誰にとっても分かりにくいものです。結果として燕返しは、この下からの攻撃で相手を打ち負かす技です。
下からの攻撃は他のスポーツにもあり、有名なのがボクシングのアッパーカットです。
ボクシングのアッパーカットは下からの攻撃ですので、いくら動体視力が良くても完全防御は難しいでしょう。
■塚原卜伝”一之太刀”
剣術の流派「鹿島新当流」を興したことでも知られている剣豪・塚原卜伝が編み出した(諸説あり)とされているのが”一之太刀(ひとつのたち)”です。
「一の太刀(いちのたち)」とも呼ばれますが、この技は詳細が後世に伝えられておらず、どのような技であったかはよくわからないそうです。
ただし宮本武蔵と並んで語られる剣聖・塚原卜伝の技ということもあり、今の時代に至るまで語り草として伝えられています。
■蜻蛉の構え
九州・薩摩が発祥とされ、同時代の剣術家から恐れられたといわれる流派「示現流(じげんりゅう)」が身上としていた構えです。
右手を中心に剣を高く掲げた独自の構え方で、一気に振り下ろすという豪快な技です。
一見すると隙がかなり大きいようにもみえますが、「二の太刀要らず」と言われるように初太刀で決着をつけることを前提にしているため、一撃で相手を確実に仕留めるという気迫と、示現流独特の掛け声がこの流派を強力なものに押し上げているのかも知れません。
■宮本武蔵の”二天一流”
こちらは技と言うよりも形、あるいはスタイルというべきかも知れませんが、宮本武蔵の代名詞としても知られているのが「二天一流」、いわゆる二刀流です。
本来は両手で持つものであった刀を片手に一振りずつ持つという奇抜な戦い方で、その特徴的なスタイルから剣に留まらず、二つのことを同時に行うことを表す総称としても広く知られています。(バッターとピッチャーを両方行う現メジャーリーガー・大谷選手など)
実際のところ、両手でも重さを保持するのが大変な金属の刀を片手で保持するには相当の腕力・握力が必要であり、また通常の剣術とはまるで違う動きが要求されることから、難易度は相当に高いものと思われます。
剣道にも二刀流のスタイルは存在しますが、真剣よりは比較的軽い竹刀といえども片手での扱いは難しいことなどもあってか、使用する選手はあまり多くはありません。
■真剣白刃取り
時代劇などの見せ場として登場することが多く、知名度の高い技「真剣白羽取り」。こちらも有名なので、名前を聞いたことのある方は多いでしょう。
斬りつけてきた刀の刃を手のひらで挟むという防御のための技ですが、実際に猛スピードで振るわれる金属の刃を見定めて受け止めることは達人であっても極めて難しいといわれています。
そのため、実戦で使われるようなものではなく、あくまでフィクションの世界での技であったり、パフォーマンス的なものとされています。
また、類似するものとして新陰流の「無刀取り」という技がありますが、こちらは相手が刀を振り下ろす前に懐に飛び込み、取り押さえるという柔術の類であり、こちらの方が対刀剣の技としては現実的と言えるかも知れません。
■ひとつの憧れとして
技からは少し離れますが、フィクションの世界・剣道を題材にした漫画もご紹介します。こういった登場人物に憧れるのもまた剣道の魅力ですね

六三四の剣(村上もとか)
まず、八十年代に一世を風靡した『六三四の剣』。
作者は村上もとか先生で、後に医療タイムスリップ漫画の『JIN-仁ー』を描いた方です。
主人公である夏木六三四は剣道界にその名を知らぬ者は居ないほどの人物を両親に持って生まれました。そのせいか、幼少期から身体能力が途轍もなく高く、一方で腕白な小僧でした。
それが剣道を通じて克己するライバルとの出会いや、父の死などの経験を通じて立派な青年へと成長していく、剣道漫画のバイブルと言われています。
当時はアニメ化、ゲーム化とメディアミックスを果たし、世にブームを巻き起こしました。
しっぷうどとう(盛田賢治)
続いて紹介するのは盛田賢治先生の『しっぷうどとう』です。
内向的な性格の長門烈は不良に絡まれる時に助けられた先輩に憧れを抱き、剣道を始めるようになります。
最初は性格が災いして、厳しい特訓や困難から逃げてばかりでしたが、次第に心身ともに強くなっていき、団体戦で重要な活躍をするようになります。
この作品は、ひ弱だった少年が剣道を通じて成長していくという物語の王道を押さえつつ、個人戦だけでなく団体戦である事にも注目しています。
誰が誰と戦い、どこで勝ち星を拾い、相手の強敵をどうやって封じ込めるのかといった知能戦めいた部分も見どころです。
BAMBOO BLADE(原作:土塚理弘 作画:五十嵐あぐり)
最後に紹介するのは『BAMBOO BLADE(バンブー ブレード)』です。
タイトルの意味はBAMBOO=竹、BLADE=刃。つまり竹刀を表しています。
この作品の魅力は、ゆるい部活動物な事です。
普通、スポーツ漫画となれば一所懸命に練習して汗を流し、試合に対して魂を燃やすかのように挑むのをイメージするかもしれませんが、作中ではそういったシーンは薄いです。
というのも、主役である川添珠姫は家が道場をやっているから流れで始めただけで剣道に対して強いこだわりが無いのです。
顧問の石田から団体戦に出るように頼まれるも消極的で、その後もあまり乗り気ではありませんでした。
ですが、自分とは違いやりたくて剣道部に入った仲間達と交流を深めていき、彼女の内面に変化が起きていくのが見どころです。
また、当初は頼りなく駄目な部分が多かった顧問の石田も、珠姫の変化に触れていくうちに指導者としての自覚を持っていく部分も注目です。
■まとめ
武術・武器術は洋の東西を問わず世界各地で研究・研鑽が進められてきました。
日本においては特に刀や槍などを用いた武器術が発達しましたが、その発展は戦がなくなって武士・武芸者の役割が激減し、存在意義を問われ始めた江戸時代からというのが何とも興味深い話です。
実戦では刀だけではなく銃や投石、煮えた油、爆薬など殺傷に使えるものは何でも使っていたため、見た目にも洗練された「技」は争いの少ない時代の方が発展しやすかったのでしょう。
現代の剣道ではルール上有効打の認められている場所が限られていることもあって奇抜な技というものはあまり使われることはありませんが、剣の歴史を紐解くことで、思わぬところから剣の上達につながるヒントが隠されているかも知れません。