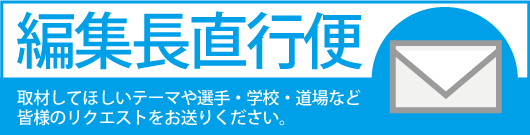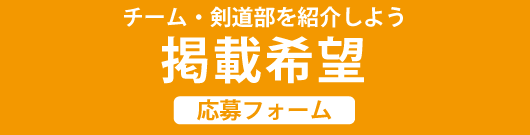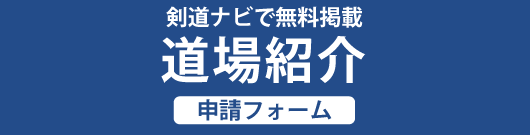実際にどんな道具が必要なのかを知っておく
■剣道防具(面・胴・甲手・垂)

面
頭部・喉を守る防具です。
面金は、顔の形に沿っており、視界を確保するために一部分だけ幅が広くなっています。喉を守るために突き垂というものがあり、喉を守るために強固に作られています。
汗の吸収や前髪などで視界を遮らないため、皮膚との摩擦防止などに手ぬぐいを使用します。
甲手
前腕から指先を守る左右一対の防具です。
手の甲はクッションになっていて綿や藁が中に入っています。手の内(てのうち)と呼ばれる手のひらの部分は薄い革でできていて、竹刀を握る際に邪魔にならないようになっています。
手の内は柔らかい部分なので破けやすく、破損した場合には、修理か革の張り直しをします。
胴
胴は、胸部・腹部を守る防具です。
胴胸という胸部分は、牛革・鹿革を使用し、胴台という腹部分にはプラスチックや竹などが使用されたものが胴として構成されます。
また胴台と胴胸を組むときに、胴台横・下を閉じ込む革をへり革といいます。ちなみに腋の下の部分を胴で守ることはできません。
垂
垂は、腰・局部を守る防具です。
垂帯・三枚の大垂・二枚の小垂で構成されており、中央にある大垂には所属する団体名と選手の苗字を付けます。
■道着

道衣
色は濃紺が一番多く、白を着ている人もいます。素材は綿の他、洗濯しやすいジャージ素材のものも学生には人気です。
夏場はメッシュタイプが風通しがよく汗をかいてもさらりとしており、綿タイプは厚手のため冬場の寒い時期に重宝します。しかし、藍染めのものは洗濯で色落ちしますので特に最初のうちは注意しましょう。
袴
こちらも濃紺が一番多いですが白もあります。
素材としては綿製を着ることが多いですが、色落ちや手入れがデリケートなため、学生にはしわになりにくいポリエステル製のものも人気です。
■竹刀

竹刀
文字通り竹で作られた刀であり、相手を打突するために使われます。
現在では竹以外の素材(カーボン製)で作られた竹刀も使われています。
竹片を四本合わせ、鹿などの革で作られた部品で纒めて作られており、剣先からは一本の弦が張られています。
鍔(ツバ)
一般的に、「竹刀」とは竹刀の竹の部分を指しており、このままでは稽古も試合もできません。
刀と同じで、手先には「鍔(つば)」という丸いものを取り付けます。
鍔は水牛革製、プラスチック製が多く、穴があいた円盤状になっています。ゴム等でできている鍔止めを使い固定します。
この鍔にはサイズがあり、竹刀の大きさ(太さ)と鍔のサイズを合わせて購入することが必要です。
本革のもの、樹脂製のものなどありますが、学校の試合ではカラフルな色付きのものは禁止という場合が多く、茶系(肌色のような)の普通のものを準備しておくようにしましょう。
手入れ具
この他にも、竹刀の手入れをする油やササクレを直すヤスリなどを準備する場合もありますが、小学生の高学年や中学生以上になれば、徐々に揃えておく
■袋類

竹刀袋
竹刀と鍔を収納する袋です。
普段の稽古には必ず竹刀袋に入れて持ち運びます。布製のものや、革製のものなど素材も多数あり種類は豊富です。
学校・道場単位でお揃いのものを持つことも多いため、購入する前に確認しましょう。
竹刀は消耗品のようなものなので、常に2~3本は袋に準備しておくのが基本です。
道具袋
面・胴・甲手・垂の剣道防具を収納しておく袋です。
普段の稽古や試合に行く際には必ず道具を入れて持ち運びます。
こちらも布製のものや革製のものなどありますが、初心者は剣道具の大きさに合わせたものを選ぶと良いでしょう。
特に小学生は両肩にもてるリュックタイプが持ちやすいです
■他に必要なもの

面手拭(手ぬぐい)
面を着ける時に必要です。
頭に巻いてから面をすることで後頭部への打撃から頭を守ったり、肌と面が直接触れることを防ぐため、汗で面が劣化しにくくなるなどの効果が得られます。また、面の方が少し大きい場合、フィットさせる役割もあります。
汗を吸いとってくれる役割もあります。
手ぬぐいは稽古をするとすぐに汗で濡れてしまいますから、常に2枚程度は準備しておくと良いでしょう。
試合の時には全員がお揃いの手ぬぐいをすることが多いため、試合用も準備しておきます。
使い方
手ぬぐいは巻き方が決まっています。
頭に巻くにはそれなりの長さが必要であるため、手ぬぐいは少し大きめであることが望ましいです。
サイズに関しては年齢にもよりますが、小学生と高校生なら当然面手拭の大きさが変わってきます。
一般的に小学生であれば90センチのサイズのものがベストではないでしょうか。
高校生になれば100センチから120センチ。120センチは少し大きいですが、愛用している人も多いです。
また、厚手すぎるとうまく巻けないだけでなく、面の装着が難しくなるのでタオルでの代用は難しいです。
選び方
使用する手ぬぐいは、基本的に色やデザインに規定はありません。
面を着けてしまえば周りからは見えないため、お祭りなどでもらうものでも十分です。また、昇段審査などでもらえる場合もあるようです。
自分の好きな文字を印刷した手ぬぐいが欲しい、チームで手ぬぐいを統一させたいと考えている人にはオーダーメイドで手ぬぐいを作ることも可能です。
手ぬぐいに印刷する文字で人気なのが『不動心』『心』『明鏡止水』『文武不枝』などです。
試合前など、面を着ける前に手ぬぐいに書かれた言葉を読んで心を落ち着かせるのを習慣にするのもいいですね。
プリントと注染の違い
『プリント手拭い』と『注染手拭い』があります。
前者はインク等を用いて機械的に印刷したもの、後者は染料を注ぎ込んで色を付けたものです。
特にどちらが良いかというわけではなく、使うのはあくまで本人の好みになってきます。
上級者やベテランは昔ながらの注染手拭いを選ぶことが多く、若い方は気軽に使えるプリント手拭いを使われることが多いようです。

木刀
昇段審査には審査項目に日本剣道形があります。このとき用いられるのが木刀です。
ただ木刀は重さも長さもあるので慣れないと扱いも難しいもの。ですから形稽古でも最初は竹刀を使うこともあります。
特に規定はありませんが、中学生以上は101.5cmの大刀(だいとう)を使うのが一般的です。
日本剣道形とは?
剣道の基本的な攻防を十本の技に集約し形として編んだもので、七本の太刀の形と三本の小太刀の形から構成されています。
内容は、打太刀はより段位・経験のある者、仕太刀はそうでない者が行ない、打太刀が先で仕太刀が技を用いて相手の攻撃に応じて技を使って勝ちます。
一本目
打太刀は諸手左上段を、そして仕太刀は諸手右上段に立ち、打太刀は左足から仕太刀は右足からそれぞれ進み、間合に接した際に打太刀はタイミングを見計らって右足を踏み出して仕太刀の正面を打ちます。
二本目
打太刀と仕太刀、それぞれが右足から進んで行き、間合に接した際に打太刀はタイミングを見て仕太刀の右甲手を打ちます。
三本目
打太刀と仕太刀、それぞれ右足から進んで行き、間合に接した際に相中段になります。その際に打太刀はタイミングを見計らい、刃先を仕太刀の左に向けて右足から踏み込みながら鎬ですり込みます。
四本目
打太刀は八相の構えを仕太刀は脇構えになり、それぞれ左足から進み間合に接した際に打太刀八相の構えから諸手左上段に、そして仕太刀は脇構えから相手の正面に打ち込みます。
各形は単純にメニューをこなしていくだけのものではなく、各動作間の仕草や発声なども重要なポイントです。
練習の際には、各動作の精度を高めるのはもちろんのこと、一連の流れと重視し、常に気持ちをこめて臨みます。
どれから揃えればいいのか

剣道の道具類はざっとあげるとこんなものでしょうか。では、実際にどうやって揃えていくのがいいのでしょうか。
■まずは竹刀から
防具を揃える場合には、まず、竹刀が一番最初となるでしょう。
初心者は数か月の間は基本練習といわれる、足さばきや素振りなどの練習が中心となります。
最初から防具を付けることはありませんので、様子を見ながら準備しても間に合います。
自分の身長などに合うサイズの竹刀を2本程度は準備しておきましょう。
また、竹刀を入れる竹刀袋、鍔も必要です。稽古に行く際には袋に入れて持ち歩きます。
■防具はある程度慣れてからでも大丈夫!
次には、甲手が必要になります。
素振りの後に面を付けずに打ち込み稽古をしますが、その際に甲手が必要となる場合があります。
しかし、面・胴・甲手・垂と一式のセットで購入するほうがお得な場合が多いため、甲手を準備するころには防具一式を準備したほうが良いでしょう。
また、防具を入れる防具袋や手ぬぐいも準備しておきましょう。
防具を一通り揃えた後は、順に予備の竹刀や手ぬぐいなどの替えを増やしていきます。
防具は一度購入したら数年は使うものですので、大事に扱いましょう。
小さいお子さん向けの道具は?
初心者であっても、上段者であっても、基本の道具に変わりはありません。
もちろんグレードはありますが、学生の内は成長期でもあるため、初めは手ごろな道具を揃えるのも良いでしょう。
■防具袋も忘れずに
防具一式を購入するときは、防具袋も購入しておきましょう。防具袋を選ぶポイントは、道具の大きさと持ち運ぶ手段などを検討することです。
小学校低学年、高学年、中学生、高校生、大学・社会人などでそれぞれ使いこなせる種類があります。
両肩に背負うタイプ
ランドセルのように肩に背負うタイプです。剣道具がまだそれほど大きくない小学生の低学年などにおすすめです。
背負うことにより、移動中は両手があきますので、稽古に行くときも危険が少ないでしょう。
また、剣道具は意外と重さもありますが、小さな子供でも持ちやすいでしょう。収納すると、袋の形は三角形になり安定もします。
肩にかけるタイプ
小学生の高学年や中学生以上になると、剣道具のサイズも大きめになるため、背負うタイプには入りきらなくなります。
そのため、ゆとりのある肩掛けタイプを使う人が多いでしょう。このタイプはかなり長く使うことができます。
ローラーが付いたタイプ
スーツケースのように足にローラーが付いたタイプは、遠征が多くなる高校生や、大学・社会人などが多く使っています。
肩掛けタイプは道具は十分に入りますが、移動の際には重さがあるため電車などでは不便を感じます。
このような場合に、ローラー付きなら、簡単に引いて移動することが出来るため、女性でも楽に運ぶことができるでしょう。遠征の時にも便利ですね。
何歳のときに剣道をはじめるかにもよりますが、小学生の初心者なら背負うタイプ、中学生からなら肩掛けタイプ、さらに遠征が多いような学年ならローラータイプという選択がおすすめですね。
■必要な物から揃えていこう!
このように、習い始める前に道具を準備する必要はありません。
また、自分の体形や腕力に合う道具をきちんと選ぶためには、始めてから経験者や武道具店などにアドバイスをもらいながら用意するほうが間違いないでしょう。
稽古のあとは乾燥させるなど、普段から手入れをすることで長く使うことができます。