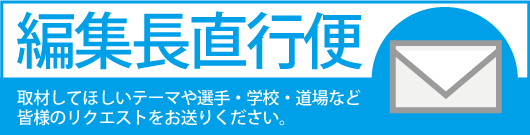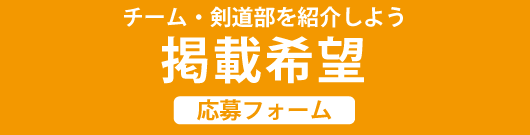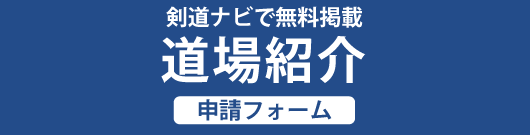これから始める人の不安や疑問にお答え
まったく未知の状態から剣道を始めるにあたって、不安や疑問はつきものです。
ここでは、これから剣道を始めてみたい人が気になるようなことに対して、お答えしていきたいと思います。
■剣道って”痛い”ですか?

稽古の様子を初めて見た時に「痛そう!」と不安に思う人は少なくないと思います。
竹刀という竹でできた棒で叩かれるなんてなかなか経験することはありませんから、当然の疑問だと思います。
実際に稽古をしてみると、痛い思いをすることがたくさんあります。どういう時に痛い思いをするのかというと、防具で保護されていない部分を打たれてしまった場合です。
剣道具は、頭、手首、胴体をカバーできるように作られており、試合で1本を取れるのもその部位を打った時です。面、小手、胴の3箇所です。
高校生以上になると、喉元を突く『突き』という技が加わります。これらの箇所を正しく確実に打てるように日々稽古を重ねるのですが、初めて間もない人は正しく打てない場合があります。
よくあるのは、小手を打とうとして、防具で保護されていない腕を打ってしまったり、胴を打とうとして脇を打ってしまったりします。
この脇を打たれるとしばらくうずくまってしまうほど痛いです。
初心者のうちは…
さらに、初心者の方ほど打つ時に体が力んで、力いっぱい打とうとするため痛みは倍増です。熟練の方との稽古ではこのようなことは滅多に起きません。
打突部位を正しく打ち、そのうえ力みもなく、程よい力加減の打突ができるようになっているからです。
しかし、初心者のうちはその力加減も難しいでしょうから、痛さはお互い我慢することになります。
足の痛み
その他には、裸足で稽古をするため足に痛みを感じることがあります。
すり足をしていると足の裏の皮がむけたり、踏み込みを始めるとかかとが痛くなったりします。
最初は大変ですが、正しい動きができるようになると、痛くなることはほとんどありません。
先輩や先生の動きをよく真似して、無理のない体の動きを目指しましょう。
■臭いというのは本当?

剣道は臭いというイメージを持つ人も多いでしょう。そのイメージは本当の話です。
使い続けた防具は独特の臭いがします。なぜ臭うのか、また、臭いを少なくする方法などについて解説します。
臭い匂いは防具から
稽古や試合をした後の防具は、汗の臭いとも違う少しツンとした独特の臭いが出てきます。
上着や袴などの道着は洗濯をすることももちろんあるのですが、防具類は基本的には洗わないというのが今までの常識でした。
防具は革などで出来ているため気軽に洗うことができなかったのですが、最近は防具を傷めない専用の洗剤が開発されたり、丸洗いのできる防具も出てきているため、防具の洗浄に対する意識は少しずつ変わってきているようです。
しかし、人によっては防具を洗わない期間が数年、数十年に及ぶことも普通にあります。そのため、稽古のたびに汗はしみ付いていき、だんだん臭うようになります。
中でも一番臭うのは「甲手」です。甲手は手袋のように手にはめていますので、その中は汗が閉じこもります。中で蒸れている状態ですね。
そのため、とても臭ってしまうのです。稽古のあと、手にもその臭いが移っているため、防具を外してもその人から臭いがする感じがあります。
臭いを防ぐ方法
例えば、甲手に関しては下に手袋をはめるだけでもかなりの効果があります。
手袋は専用で販売されてもいますし、自分で手ぬぐいなどで作ることもできます。
また、稽古の後には防具類をよく乾かすということも大切です。防具を汗で濡れたままにしておくと、臭いが酷くなるばかりか湿気でカビが発生する原因にもなりかねません。
特に梅雨時や夏場は防具袋の中が蒸れやすいので、必ず広げて干しておくと良いでしょう。乾燥させることで臭いはかなり軽減できます。
また、消臭スプレーをかける方法もありますが、まれに白く跡が残るとも言われていますので目立たない部分で試してみることをおすすめします。
■上下関係が厳しそう?

剣道は礼儀作法が厳しい武道であることから、上下関係にも厳しいとも言われていますが、実際はどのようになっているのでしょうか。
それぞれの所属団体によって実態は異なりますが、礼を重んじる競技ですのである程度の厳しさがあるのが現実です。
剣道では先生や先輩から上下関係を通して様々なことを学びます。
とはいえ、理不尽なことを言われたり、いじめのような行為を受け、どうしても我慢できないという時は必ず周囲の人に相談するようにしましょう。
礼儀というのは立場の上下に関係なく、互いを尊重することが基本です。相手が自分より下の立場にいるからといって好き勝手な言動を投げかけていいわけではありません。
先輩は先達として後輩の規範となるべく自分を律し、後輩はそんな先輩の気持ちに感謝しながらお手本として学んでいく、そういった関係が理想ではないでしょうか。
あなたがこれから剣道を始めるにあたって、いずれ来る後輩に対して恥ずかしくない礼儀を身につけられるように励むことが大切です。
そうすれば、あなたより後に入門した後輩たちは自ずと先輩を慕ってくれることでしょう。
■精神力が鍛えられる?

武道のスローガンのひとつに「心・技・体」というものがあります。
武道はただ体を鍛えるだけでなく、精神の研鑽にも励まなければなりません。大げさな言い方ですが、要するに「鍛えて強くなるからには、心が弱いままではダメだよ」ということです。
古代ギリシャの詩人・ユウェナリスは「健全な精神は健全なる肉体にこそ宿れかし」という言葉を残しました。
よく「健全な精神は健全な肉体に宿る」という誤った解釈をされることで有名なこの言葉ですが、本来は健全な肉体の持ち主こそ健全な精神を持つべき、という意味なのです。
つまり、ただ漫然と身体を鍛えていても精神までは鍛えられません。日々の練習や試合での経験から精神修練の意義を見出せるかどうかも大事です。
精神の鍛え方
精神を鍛えるといっても、具体的にどうすればいいのかと言われるとなかなか難しいものです。
しかし、精神力というのは自分の内なる力であるため、自分の気持ち次第で鍛えられるということでもあるのです。
最も基本的なところで精神を鍛える方法を一つ紹介してみましょう。それは大きな声でしっかりと挨拶をすることです。
恥ずかしいとか、面倒という理由から挨拶をしない人もいますが、そんなネガティブな気持ちと向き合いながら、それでも元気よく挨拶をしてみましょう。
そういった後ろ向きな気持ちに打ち勝って挨拶をすることができた、というのが小さな達成感になります。
これを毎日繰り返していけば「自分は元気に挨拶ができる人間だ」という自信が少しずつついてくるようになるでしょう。
精神力というものは自信と密接に繋がっています。普段の稽古でも、自分にできることを少しずつ増やし、小さな自信を積み重ねていけば精神はより鍛えられていくことでしょう。
■剣道における二刀流というスタイルはあるの?
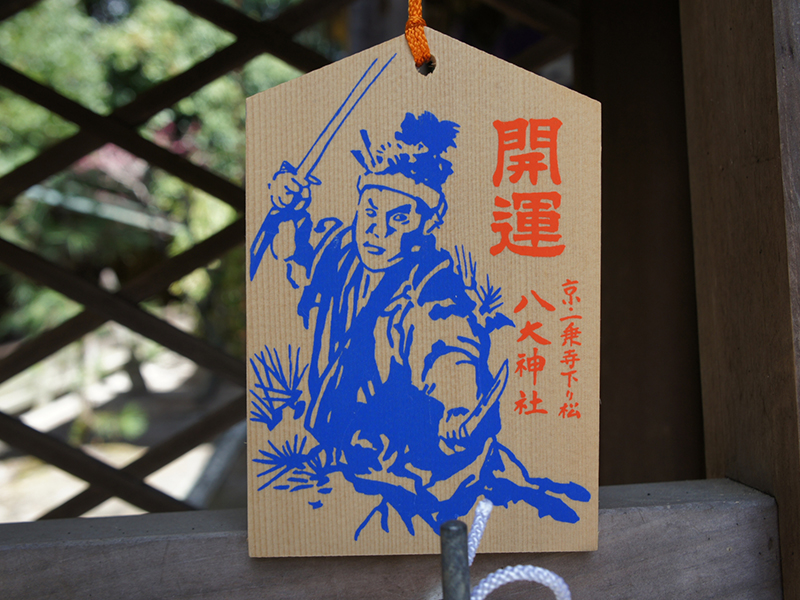
一般的にイメージされる剣道のスタイルと言えば選手が竹刀を一本ずつ持って戦う形ですが、竹刀を二本使用する、いわゆる『二刀流』も実はルール上認められた行為なのです。
その場合、選手は大刀、小刀をそれぞれ右手と左手に持ち戦うスタイルとなります。
ただし、一部試合での使用を認められていない場合があります。まずは中学生、高校生の公式戦です。
また高校生以上の大会であっても一部二刀流を禁止している大会もあります。
二刀流は実際強いのか?
二刀流が試合において有利かと言えば、どちらとも言えないというのが実情です。
単純に二本あるから強いと思う方は多いのですが、実は鍔迫り合いにおいて小刀を下に、大刀は上に構えるルールや、有効打突の決まりなど制限が多いのが二刀流です。
また、比較的軽い竹刀とはいえ、片手で扱うには相応の腕力が必要になります。使いこなすにはそれなりの訓練が必要になってきます。
しかし戦い方は様々で型にはまるととても強い戦い方です。総じて言えることは制限はあるが自由度が高い戦い方が二刀流と言えるでしょう。
また二刀流の場合、大刀と小刀をそれぞれ購入しなくてはなりません。小刀の価格は意外と高価なものである上、壊れやすいので多くの選手が自作しているそうです。
そのような観点からも二刀流は華やかで目立つ反面、実践するのはいろいろと大変なスタイルなのかも知れません。
二刀流を学ぶにはどうすればいいの?
では、実際に二刀流を教えてくれるところはあるのでしょうか。これから剣道を始める人、また興味がある人は非常に気になる点でもあります。
二刀流と言えば歴史上では宮本武蔵が有名であり、その影響を受けている人もいるでしょう。
確かに格好良いので憧れる人も多いですが、問題はそれを教えてくれる道場があるのかです。
そんな二刀流ですが、使い手は少ないのが現実です。
その大きな理由が剣道の指導方針であり、現代の剣道は基本形である一本の竹刀から指導するのが主流になっています。
ほとんどの人が一刀から練習を始め、そのうち一刀が体に馴染みます。そして徐々にそれが基本の形として形成されていくのです。
全国には二刀流を教えてくれる道場もあるかもしれませんが、たとえ二刀流を目指して入門しても、まずは一刀流から始めることが多いです。
一刀が体に馴染んでいくとそのままの形で極めていくことになります。実践している人が少ないぶん、教えてくれる指導者が育ちにくい、とも言われています。
■まとめ

初めてのうちは何もかもわからないことだらけで、不安な気持ちになるのは当たり前のことです。
しかし、勇気をもって一歩踏み出すことで今までとは違う別の世界が見え、自分の可能性が広がっていくことも確かです。
剣道を始めたいという気持ちと、知らないことへの不安がせめぎあっている方が、こちらの記事をみて少しでも前向きな気持ちになってくれれば嬉しい限りです。