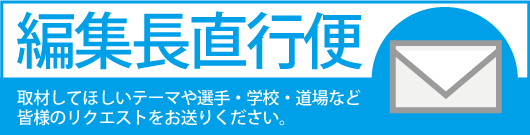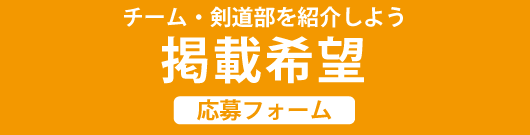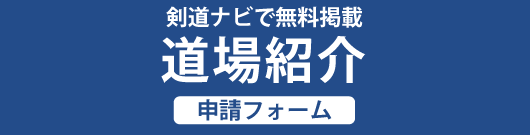団体戦決勝は、男女ともに大接戦となりました。代表戦までもつれこみ、紙一重で惜しくも敗れてしまった守谷についてはどのように見えていましたか?
守谷高校は全体的にとても良かったと思います。
とくに先鋒の福居永里子選手(3年)、次鋒の内藤栞選手(1年)は、実力が伯仲するなかで「絶対に取ってやるんだ」という強い気持ちと勢いで勝利をつかみとった印象です。

女子団体決勝、中村学園の中堅笠の攻め。この後一瞬の隙をとらえ野川からひきメンを奪う
手元をあげたところでの突き技や胴技など、守谷の選手は中村学園の剣道をかなり研究し、対策を練ってきたことが伺えました。
大将の柿元冴月選手(2年)は、昨年の宮城インターハイでも決勝の大将戦で妹尾選手に負けています。高校最後の対戦となるここで勝っておきたいという気持ちはとくに大きかったと思います。
柿元選手も中村学園の剣道をかなり研究していると思いました。
遠間からの面や水平に竹刀を振っての横からの小手など、何本か惜しい技がありました。
もともと剣さばきに柔らかさがあり、ここぞという場面では思い切った技を出すこともできる選手です。
最後は体勢が崩れたところで面に乗られてしまい、残念ながら一矢報いることができませんでしたが、この経験は必ず来年以降の糧になると思います。来年の活躍が楽しみです。
男子2位の育英も九州学院をギリギリのところまで追いつめました。今大会の育英の良さはどのあたりにありましたか?
育英高校は、先鋒から大将までどの選手もしっかり構えて打つという正当派の剣道をしているなと感じました。
レギュラー全員が、どこのチームにいっても大将ができる、そんなイメージですね。
とくに私が印象的だったのは、次鋒を務めた阿部壮己選手(3年)の戦いぶりです。

育英の次鋒阿部は終始チームを引っ張った。写真は二本勝ちを収めた準決勝
育英のなかでも一番はつらつとしていましたし、立ち上がりに胴を抜いていったりと、若々しく思い切りのある剣道をしていました。
高校生らしいというか、アグレッシブな試合運びは見ているこちらもワクワクするものがありました。
惜しい技がいくつもあっただけに、一本につなげられなかったのはもったいなかったなとも思います。
やはり実力の拮抗する勝負では、一本にする力というのが重要になりますか?
そうですね。どれだけ惜しい技があってもそこで旗があがらなければ、次はそれ以上の技を出さないと一本にはなりません。それが試合の難しさでもあるのですが……。
剣道はどれだけ当てたかを競う競技ではなく、審判を認めさせる打突ができるかできないかの勝負です。
今回は九州学院の選手の方が、そういった難しい局面での判定をものにできていました。だからこそ優勝できたのではないかと感じています。
男子個人戦は優勝候補とされていた選手が続々と敗退するなか、昨年のインターハイで惜しくも岩切勇磨選手(現・国際武道大)に負けて2位となった大平翔士選手(佐野日大3年)と、優勝候補のひとりであった水戸葵陵の棗田龍介選手(3年)を準決勝で破って勝ち進んだ加藤竜成選手(八頭3年)の争いとなりました。
大平選手は2年連続で決勝まで進出してきただけあり安定感がありました。
一方の加藤選手も、大平選手が小手にもぐる瞬間や下がる瞬間などに打った裏から面など、一本にすることはできませんでしたが惜しい打突がいくつかありました。
優勝を決めた大平選手の引き面は彼の経験値の高さがものを言った技だと思います。
試合中の大平選手の足さばきを見ていたのですが、序盤からつばぜり合いで、右足を引いて引き面を狙っているのが分かりました。
4分の時間内は、加藤選手もうまく間合をとって打たせていなかったのですが、一本が決まったときは反応できていませんでした。
延長に入り試合時間が長くなれば、どうしても集中力は途切れてしまうものです。
無理のない試合運びで、相手の一瞬の隙に狙いをすまして一本を決める。
大平選手の戦いぶりは、インターハイ個人王者たり得るものだったと思います。
女子個人戦で決勝に進出したのは、2連覇をかけた妹尾選手と、松山北の渡邊茜選手(3年)でした。”両者は昨年のインターハイでも準々決勝で顔を合わせており、渡邊選手にとってはリベンジとなる一戦でした。
渡邊選手は小柄ですが、パワーのある妹尾選手を相手にうまく戦えていたように思います。
押されながらの引き面や引き小手など、手数が多く、試合中も技が尽きることがありませんでした。
最後は間合の入り際、妹尾選手がもっとも得意とするところに引き出されてしまったため、対応できずに打たれてしまいました。それが勝敗の分かれ目になったのかなと思います。

女子個人決勝、妹尾(中村学園女子)がメンを決め、2年連続二冠に輝いた
優勝した妹尾選手は、団体戦でも個人戦でも戦い方のスタイルをいっさい変えていませんでした。
間合を潰して相手が入ってきたところを打つ。やっていることは単純なように見えますが、自分に自信がなければできない戦い方だと思います。
相手にしてみれば面に跳んでくることは分かっている。普通であればそこで出小手や返し胴を狙うわけですが、なぜ上手くいかないかというと、こちらが攻めても妹尾選手が誘いに乗ってくれないからです。
打ってきてほしいと感じるタイミングから、1テンポ、2テンポあとのタイミングで乗られるので、返しようがないのだと思います。
それに加えて、団体戦と個人戦が交互に行なわれる大会3日目でも妹尾選手からは疲労が感じられませんでした。
狙った一瞬を仕留めるいわゆる省エネタイプの剣風だとはいえ、インターハイを最後まで勝ち抜くために充分な体力を普段の稽古の積み重ねで身につけてきたんだろうなと感じました。
妹尾選手は9月に韓国で開催される世界大会でも日本代表に選出されています。
世界大会では、これまでに戦ったことのないような剣風の選手と剣を交えることになるはずです。
個人戦登録もされていますから、勝ち進めば山本真理子選手(大阪府警)や松本弥月選手(神奈川県警)など、日本のトップクラスの選手らと世界一の座をかけて争うこともあるかもしれません。
そうなったときにどのような戦い方をみせてくれるかとても楽しみですね。
世界大会という独特の雰囲気のなかでも自分の剣道を貫くことができればそれもすごいことですが、世界を相手にしたときに、どう彼女の剣道が進化するのかも見てみたい気がします。