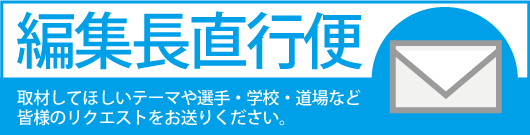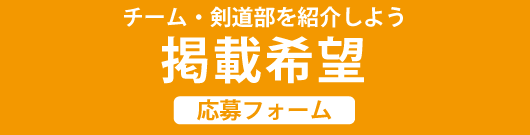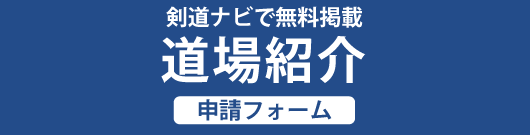木和田大起(きわだ・だいき)
昭和53年8月生まれ。教士七段。
三重県紀宝町に生まれ、三重高校から中央大学に進学。卒業後、大阪府警に奉職する。第60回全日本選手権大会優勝。世界選手権大会には2度出場し、日本を世界一へと導く活躍を見せた。現在は大阪府警察剣道上席教師の肩書きで、所属する岸和田署で警察官の剣道指導にあたる
今大会は、団体戦、個人戦の両部門でケタ違いの強さを見せた妹尾舞香選手(中村学園女子3年)の活躍がとくに印象的でした。彼女の強みはどんなところにあると、木和田さんの目には見えましたか?
妹尾選手は高校生のレベルをはるかに超越していましたね。
団体戦、個人戦とも連覇がかかる状況で、なおかつ、世界大会の代表メンバーにも選ばれていますから、プレッシャーを感じる部分もあったと思います。
ですが、どんな場面でも普段通りの〝自分の剣道〟を貫いていました。
これは、普通の高校生がなかなかできることではありません。
彼女の強さはそこにあるのではないでしょうか。

女子団体決勝、中村学園女子の妹尾が大将戦でメンを決める。これで代表戦に持ち込んだ
団体戦の決勝でも、チームの勝敗が自分の手にゆだねられているなかで、大将戦で一本を取って代表戦に持ち込み、さらに代表戦でも思い切った技を打って勝利を勝ち取りました。
あれは、ある種、持って生まれた才能だと思います。
メンタルはある程度までは鍛えることができますが、勝負がかかった場面であのような技を出すことができる選手は、ほんのひと握りです。
技術もメンタルも、高校生レベルを基準にすれば完璧に近い。今年のインターハイでは、そんな彼女に勝てる選手が出てこなかったという印象です。
団体戦でも個人戦でも、まさに破格の強さをみせていたと思います。
中村学園女子高校は妹尾選手が入学してから、インターハイ女子団体を3連覇しています。やはりその貢献度は高いと感じられますか?
今大会に関しては、中村学園の優勝は大将の妹尾選手と副将の諸岡温子選手(3年)、この二枚看板がしっかり軸となって力を発揮した結果だと思います。
とくに私が注目したのは諸岡選手です。
どうしても妹尾選手の影に隠れてしまいがちですが、諸岡選手がいたからこそ、妹尾選手も実力を充分に発揮することができたという側面もあると思います。

女子団体決勝での諸岡。この試合は引き分けだったが、いい流れをつくって妹尾につなぎ、逆転のムードをつくった
決勝戦での諸岡選手は、一本でも打たれたら負けてしまう状況下においても有効打突を取りにいこうとする強い攻めの姿勢が見てとれました。
「自分は守りきるからあとはお願い」というタイプではありません。
終始攻めを緩めず、なおかつ相手にも打たせないという戦い方は、当然のことながらすごく難しい。
それでもあのような剣道を体現できるのが諸岡選手の強さ。後ろに控える妹尾選手との信頼関係もあったでしょうし、私がなんとかする、というプライドもあったと思います。
諸岡選手がつねに良い流れをつくり出して妹尾選手にバトンを渡す、これが中村学園3連覇の大きな鍵だったように感じます。
〝自分で決めよう〟という気持ちは、中村学園のどの選手からも感じられました。
先鋒から中堅までが1、2年生で構成されていましたが、妹尾選手や諸岡選手が後ろに控えていることで、下級生も安心感を持って試合ができている印象でした。
凌いで引き分けに持ち込み後ろにつなげよう、ということではなく、のびのびとやるなかでも自分たちで決めたいという気持ちで剣道をしているように見えました。
とくに中堅の笠日向子選手(1年)は、先鋒と次鋒でリードされてかなりのプレッシャーがかかっていたにもかかわらず、それに打ち勝って白星を奪い、後ろにバトンをつなぎました。
まだ1年生の彼女にとっても、来年以降の自信になる試合となったはずです。
スコアだけを見れば接戦、勝負は代表戦までもつれていますが、やはり中村学園の選手は個々の能力も高かったと思います。
副将の諸岡選手がキーマンだったというお話ですが、最近の高校剣道では副将に実力のある選手を置くチームが増えてきたように感じます。
そうですね。私が高校生だった当時は、一般的に大将の次に大事なポジションは中堅とされていたので、中堅に力のある選手を配するケースが多かったと思います。
ですが、今の高校剣道は副将と大将に強い選手を据える傾向へと戦術が変化してきたように感じます。
実は警察剣道や日本代表においては、副将はかねてからとても重要な役割だと認識されています。
私が世界大会に出場させていただいたときも「副将が一番大事だ」とつねづね言われていました。
世界大会の歴代代表を見ても、日本が前回大会敗戦のリベンジとして臨んだブラジル大会では、副将と大将に高鍋進選手(神奈川県警)と寺本将司選手(大阪府警)を配置していましたし、さらに遡れば1997年の日本大会では、宮崎正裕先生(神奈川県警)と石田利也先生(大阪府警)という現日本代表の両監督が後衛に座っておられました。
やはり二枚看板のイメージは強いと思います。
木和田さんも大阪府警や世界大会で副将というポジション多く経験されています。
副将はとても大変なポジションで、苦労したというのが率直な感想です。
調子が出ずに伸び悩んだ経験もあります。
「自分の後ろには絶対的な大将がいる」という安心感がある一方で、自分の役割はなんだろうと模索する日々でした。
自分が負けて大将の先輩に迷惑をかけてしまったこともあります。
副将は試合の状況によって、自分で勝負を決めることもできるし、チームにピンチを招く可能性もあるポジションです。
だから戦い方がすごく難しい。私の場合は、足をつかって守れるようになったことで、剣道の幅が広がり、副将でも活躍できるようになりました。
九州学院の米田敏郎監督や中村学園の岩城規彦監督などいわゆる名将と言われる監督たちは、日ごろ練習試合を繰り返すなかで副将の重要性を肌で感じているのかもしれませんね。
九州学院の副将をつとめた小川大輝選手(3年)も、準決勝の奈良大附属戦で、自分が勝たなければ後がない状況で展開をひっくり返し、チームに勝利を引き寄せる大きな役割を果たしました。
九州学院の歴代チームを見ても、近年では梶谷彪雅選手(現・明治大)が副将というポジションで活躍していましたよね。
米田監督の副将に対する信頼感が分かります。
妹尾選手も去年は副将を経験していましたし、やはり副将が強いチームは上位に進出してくる可能性が高いように思えます。
大将が強いのは当たり前、だからこそ副将の働きがより重要になってきている。
今回のインターハイを見ていてとくにそう感じました。
男子の決勝戦は1(1)─1(1)で大将戦にもつれこみました。接戦を制した重黒木祐介選手(3年)の評価についてもお願いします。
玉竜旗では島原高校の黒川雄大選手(3年)に惜しくも負けてしまったとはいえ、彼の勝負強さは目を引くところがあります。
ガツガツ攻めていく剣風ではありませんが、間合をつぶしながら入っていくので相手は何もできない。
そして一瞬のチャンスを見極め、小手や引き面といった得意技でしっかりと決める。
とくに団体戦決勝の大将戦は、彼の得意な部分が光っていたと思います。

男子団体決勝、大将戦で九州学院の重黒木がひきメンを決めた
相手の松澤尚輝選手(育英3年)が間合に入ってくるところを徹底的に潰してチャンスをつくらせなかった。
延長に入って、それまで打っていなかった引き技で一本を決めましたが、決定打となった引き面は左にまわり左体重にさせてから右にさばいての面。まさにセオリー通りの引き面です。
あのスピードで崩されてしまうと防御をするのは難しい。
あの瞬間まで〝ここぞ〟という技をとっておいたのかもしれませんね。