試合ルールを簡単に押さえておこう!
試合に臨む上で知っておくべきルール 試合は普段の稽古の成果を出す場所のひとつです。 今まで頑張ってきたことをしっかりと出し切るためにも、ルールを理解して臨みたいですね。 時間と勝敗、そしてやってはいけないことも含めたルー…
 剣道を知る
剣道を知る試合に臨む上で知っておくべきルール 試合は普段の稽古の成果を出す場所のひとつです。 今まで頑張ってきたことをしっかりと出し切るためにも、ルールを理解して臨みたいですね。 時間と勝敗、そしてやってはいけないことも含めたルー…
 試合リポート
試合リポート初の個人タイトルが関東大学女王! 5月19日、東京武道館において第50回の節目となった関東女子学生選手権大会が開催された。 決勝は昨年本大会3位で高校時代にインターハイ個人を制している竹中美帆(筑波大3年・島原高校出身)…
 上達のコツ
上達のコツ試合の前に考えるべきこととは 試合に臨む前に緊張しないように、冷静さを常に持ち続けるように心を落ち着けておく必要があります。 しかし、競技である以上、一番に思うことは『勝ちたい』この一点に尽きます。 そのためにはどんな心…
 試合リポート
試合リポート教士の部 教士の部では一本の判定が下される。 最近、ではなくざっと記憶をたどっても20年ぐらい前から、時間内に一本も決まらず引き分けという立合が多くを占めるようになってきている。 通常の試合が5分であり、全日本八段戦など…
 大会情報
大会情報3月 [table id=114 column_widths=”40%|20%|25%|5%|10%”/] 4月 [table id=115 column_widths=”40%|20…
 名勝負物語
名勝負物語20世紀最後の全日本選手権 栄花直輝が全日本選手権で優勝を果たすのは9回目の出場のときで、これは西川清紀と並ぶ遅い記録だった。 平成4年に25歳で初出場、7年に初のベスト8、9年に初の3位と順調に戦績を上げて行った。 ま…
 名勝負物語
名勝負物語大会で10年ぶりに生まれた20代の優勝者 昭和59年から全日本選手権には「六段以上」の出場資格制限が設けられた。 あまりに勝負に走った「当てっこ剣道」が横行しているからという高段者の意見に沿ったものだったが、それによって…
 名勝負物語
名勝負物語3連覇は、当時大きな話題になり、今も輝きを失っていない 第二次世界大戦中、戦後の剣道禁止時期、玉竜旗大会(当時は大会の名称が異なる)には中断があったが、中断前の最後の大会となった昭和17年、戦後復活第1回の昭和30年とも…
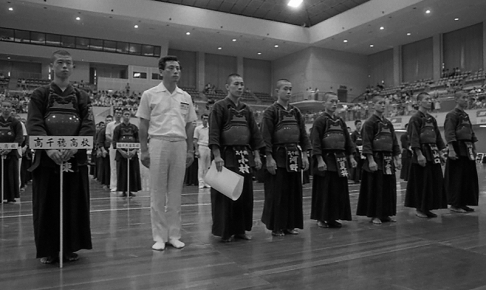 名勝負物語
名勝負物語昭和61年の玉竜旗大会(男子)は、PL学園(大阪)が2年生大将鍋山隆弘の活躍で2度目の優勝。翌年も鍋山を軸に連覇を狙った。 決勝で相対したのは、前年のインターハイ男子決勝でPL学園を下し、女子団体をも制してアベック優勝を…
 名勝負物語
名勝負物語昭和47年にインターハイ男子団体で初優勝し、計7回優勝を果たしている大阪のPL学園 とくに昭和50年代は八代東(熊本)と並ぶ高校剣道の二強というべき存在だった。 そのPL学園をもってしても九州勢の牙城は高く、最初に玉竜旗…