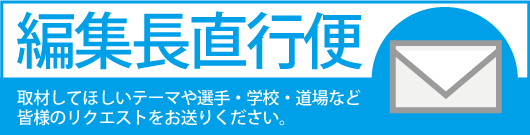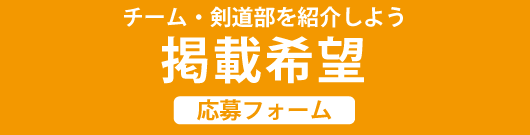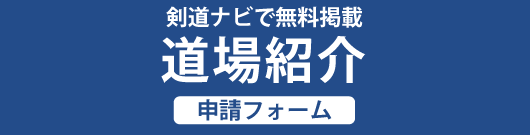古くから今に伝わる剣道の「教え」について、先人たちはどんなふうに説いてきたのか。
現在その意味が変わらずに伝わっているのか、微に入り細をうがちながら紐解いていくコーナーです。
剣先と拳を見よと説く 一刀流の「二の目付」
「遠山の目付」「観見の目」など「目」「目付け」については、古くからさまざまな教えが伝わっています。
「どこを見るか」の具体的な教えと、「どうやって見るか」の精神的な教えを、流派剣術の時代から昭和までの文献からピックアップし、あらためて考えてみることにします。
■眼の”付け方”
高野佐三郎の『剣道』(大正4年刊)は、現代剣道の技術解説書の原典といえます。ここでは、同書の記述を軸にして、時代を遡りつつ下りつつ、目付についての教えを紹介していくことにします(なお、『剣道』を含め、時代が古い書物に関しては編集部で現代的表現に改め、意訳した)。
『剣道』を改めてひもといてみると、「眼の付け方」という項目が見つかります。最初は予想通り「遠山の目付」についてふれていますが、それに続けて書いているのが「二(ふたつ)の目付」です。
佐三郎が「古来これは二の目付と言われ」と書いている通り、これは一刀流に伝わる教えでです。
同じ一刀流系統でもっと時代を遡ると千葉周作が「北辰一刀流十二箇条訳」の一条として次のように記しています(『千葉周作遺稿』に収録)。
二の目付というのは、敵を見るときに二つの目付があるということだ。まず敵を一体に見る中に目の付け所が二つある。切先に目を付け、拳に目を付けることだ。この二つである。敵の拳が動かなければ、打つことはできない。切先が動かなければ打つことかなわず。これが二つの目付である。
また、敵にのみ目を付けて己を忘れてはならない。我も知り、彼を知るということを実践するための二の目付である」
相手の剣先と拳の二カ所を見なさいという具体的な教えで、現在ではあまりそういう教え方はされていませんが、かつてそう教えていたということは参考にしていいのではないでしょうか。千葉周作は、敵ばかりに注目して自分を忘れてはならないという、精神的な内容にも触れています。

■敵の顔を見よ、と説いた若き日の宮本武蔵
宮本武蔵の「目」についての教えをひもといてみましょう。
「観見の目」の教えが有名な宮本武蔵ですが、『五輪書』よりずっと早く、24歳で吉岡一門との戦いに勝った後、最初に書いた兵法書である『兵道鏡』の中には、次のような記述があります。
ここでは「顔を見なさい」ときっぱりと言い切っています。ただしそれに続けて、
と書いています。たとえがなかなか難しいですが、後年の『五輪書』などに通じる部分も感じられます。
そして興味深いことには、『五輪書』の風の巻「他流に目付という事」の項目で、武蔵は『兵道鏡』の記述を自ら否定しています。
たとえば蹴鞠(けまり)をする人は、鞠を注視しているわけではないのに、さまざまな技法で巧みに蹴ることができる。ものに習熟することによって、いちいち目で見なくてもすむようになるのだ。また曲芸などをする者も、その道に習熟すれば戸板を鼻の上に立てたり、刀を何振りも手玉にとったりするときに、いちいち見ているわけではないが、普段から扱い慣れていることによって、自然とよく見えるようになるのだ」
後で述べますが、『五輪書』の中では「観の目」のことや「敵の太刀を知り、敵の太刀を見ない」ことなどを強調しており、「顔を見よ」という主張は封印した格好になっています。つまり実戦を重ねていく中で、武蔵はそういう高い境地に達したと考えられます。
しかし、29歳まで六十何回かの真剣勝負を重ねた武蔵が、その勝負の時期のまっただ中で書いた『兵道鏡』には、実際の戦いにおいてはより有効な、真実に近い内容が書かれている、とも考えられるのではないでしょうか。